特定技能の資格取得時に必要な「特定技能評価試験」は何?
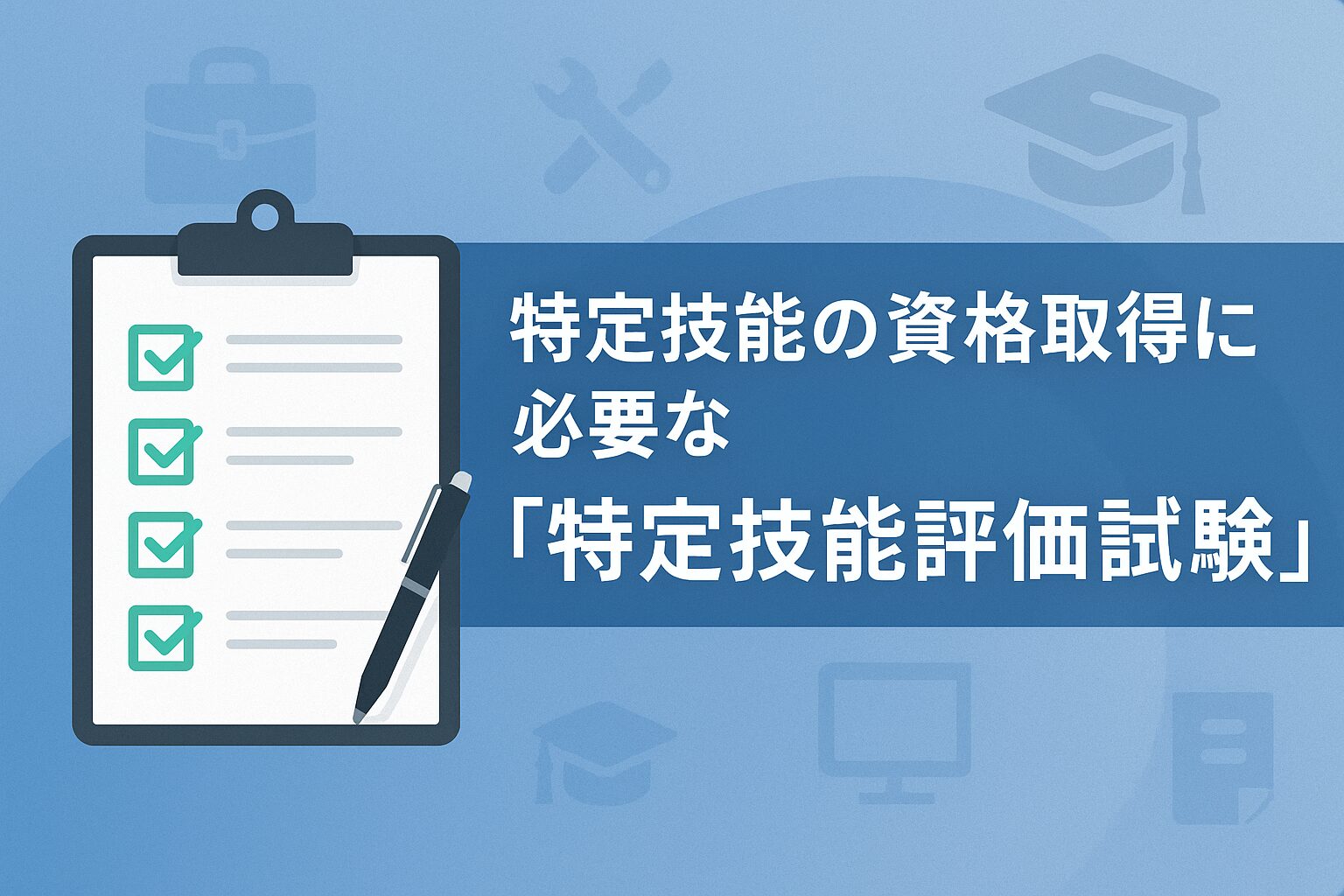
「特定技能」で就労するには、分野ごとの技能試験(評価試験)と、原則として日本語能力の要件(JFT-BasicまたはJLPT N4相当など)を満たす必要があります。本記事では、2025年時点の公式情報を踏まえ、試験の全体像・申込方法・よくあるつまずきまでを実務目線で整理します。
目次
1. まず押さえる:評価試験の全体像
- 特定技能1号(SSW(i)):分野ごとの技能評価試験+日本語要件を満たせば申請要件の一部を充足。
- 特定技能2号(SSW(ii)):より熟練レベルの業務を想定。分野別の2号評価試験に合格することが基本。
- 試験の実施主体は分野ごとに異なる(例:製造、外食、宿泊、建設など)。試験日程や受験地は毎月のように更新されます。
※ 試験に合格しても、在留資格の許可が自動で保証されるわけではありません。雇用契約や受入体制など、在留審査で求められる他要件の充足が別途必要です。
2. 対象分野と2号の取り扱い(要点)
- 特定技能1号は16分野で運用(介護、宿泊、外食、飲食料品製造、建設、製造関連ほか)。
- 特定技能2号は対象分野が拡大済。長期就労や家族帯同が視野に入るケースもあり、分野別の最新要領を必ず確認しましょう。
- 一部分野(例:介護など)は現時点で2号の対象外の取扱いが残るため注意。
※ 詳細な分野リストや2号の可否は公式サイトで最新を確認してください(制度改正が続いています)。
3. 試験の種類と内容(例)
評価試験はおおむね学科(知識)+実技(技能)で構成され、CBT(コンピュータ試験)や実技課題を組み合わせます。以下は代表例です。
| 分野 | 試験の例 | ポイント |
|---|---|---|
| 製造(素形材・産機・電機電子など) | 分野別の1号評価試験(国内/海外で定期的に実施) | 日程が年に複数期設定。試験地はアジア各国+日本で展開。 |
| 飲食料品製造・外食 | 分野別評価試験(1号/2号)。 外食は衛生・接客、飲食料品製造は衛生・製造工程などを出題。 | 業界団体が運営。2号試験の実施や周知も進んでいます。 |
| 宿泊 | 1号/2号評価試験(学科+実技) | 宿泊2号は監督・指導レベルが想定。CBT中心で海外会場も拡大。 |
| 建設 | 分野・職種ごとの評価試験(学科+実技) | 申込~受験の手順がアプリ/ポータル化。最新の開催案内を要確認。 |
※ 出題範囲・出題数・試験時間は分野別の実施要領で確認してください。例:宿泊2号は学科50問+実技20問・60分など、詳細が公表されています。
4. 受験までの流れ(共通イメージ)
- 公式サイトで告知確認:分野別の試験センター/SSWサポートサイトの「試験情報」をチェック。
- 受験者アカウント作成:試験運営(例:Prometric等)のIDを作成し、本人確認情報を登録。
- 会場・日時を予約:国内/海外会場の空き枠から選択。予約~受験~合否公表までのスケジュールを控える。
- 準備:身分証、受験票(QR/予約ID)、ドレスコードや持ち物(電卓等の可否)を各分野の受験要領で確認。
- 受験・合否確認:合否はセンターのサイトやマイページで公表。合格証明の保管を忘れずに。
5. 日本語要件の整理
- SSW(i)では、JFT-BasicやJLPT N4相当などの日本語能力を満たすことが原則。
- 試験の実施言語は分野・国により複数用意されることがありますが、在留申請の日本語要件とは別の論点です。要件の取り違えに注意。
6. よくある質問(FAQ)
Q1. 合格すればすぐに在留資格がもらえますか?
A. いいえ。合格は必要条件の一部です。雇用契約・処遇(同等以上)・支援体制・提出書類など、在留審査で求められる他要件を満たすことが必要です。
Q2. 合格の有効期限は?再受験は?
A. 有効期限や再受験の可否は分野・実施団体により取扱いが異なります。各分野の実施要領を参照してください。
Q3. 海外でも受験できますか?
A. 多くの分野で海外会場が設定されています。国・都市・日程は月次で更新されるため、直近の開催一覧を確認してください。
7. 企業側の実務ポイント(つまずきを防ぐ)
- 職務記述書(JD)と試験分野の整合:応募者の試験分野と現場の業務範囲がズレないよう、付随業務の範囲まで文書化。
- 契約の具体性:基本給・手当の内訳・控除・想定手取り、労働時間/シフト/休日/割増率を契約本文または別紙で明記。
- 最新情報の確認:分野別の運用要領・評価試験の告知は頻繁に更新。申請前に必ず再確認。
8. まとめ
「特定技能評価試験」は、分野別に要件や運用が異なる点が最大の注意点です。まずは公式サイトで最新の試験日程と実施要領を確認し、日本語要件・雇用契約書の具体化までセットで準備しましょう。分野選定や在留申請の設計に迷ったら、早めに専門家や支援機関へご相談を。
株式会社オーティル

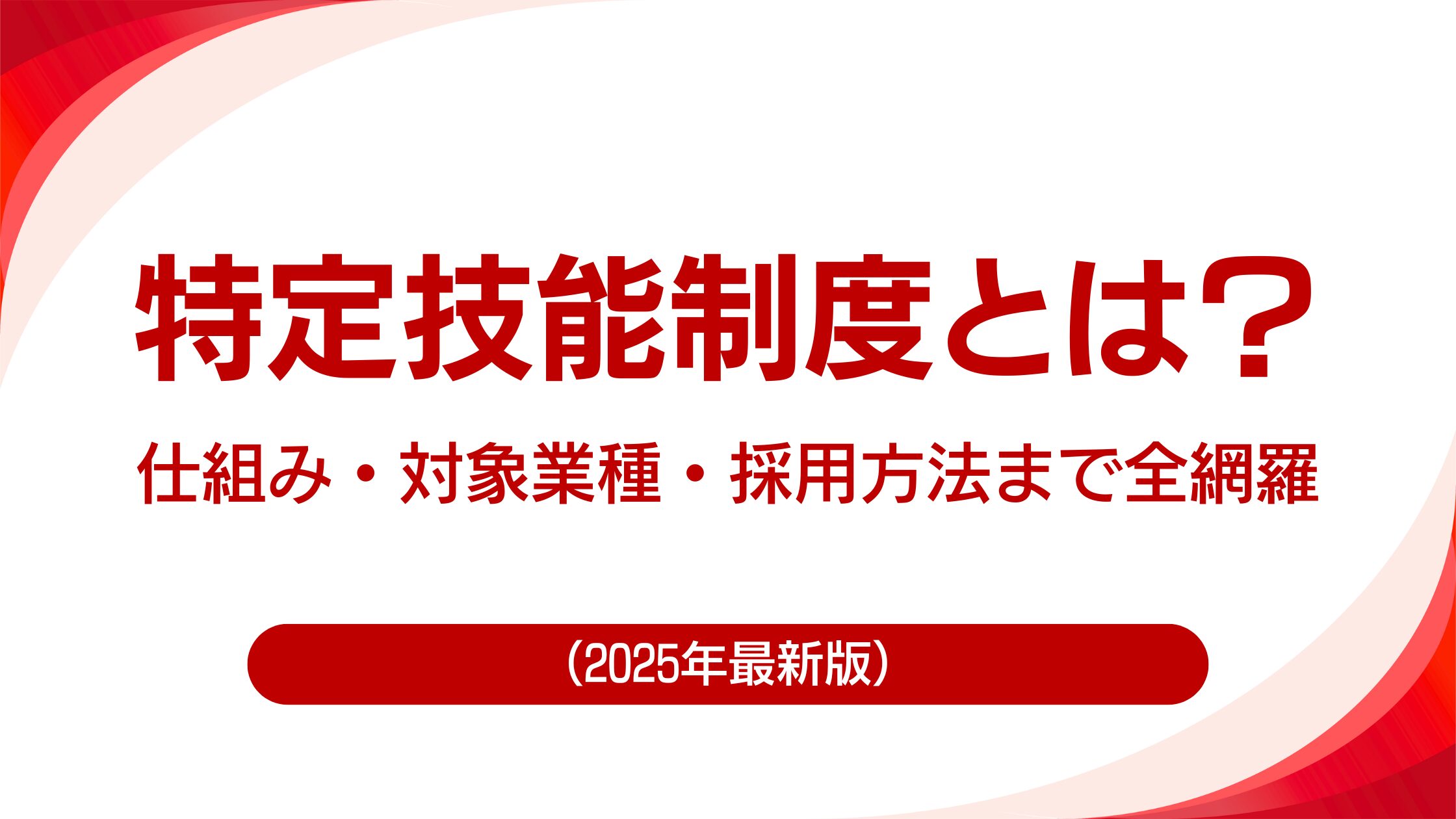
【保存版】特定技能制度とは?仕組み・対象業種・採用方法まで全網羅(2025年最新版
著者:株式会社オーティル 人手不足に悩む業界で注目されている「特定技能制度」。 しかし、制度の仕組みや対象業種、採用の流れなどが複雑で「正しく理解できていない」「…
