【2025年版】技能実習制度の現状と「特定技能」への切り替え完全ガイド
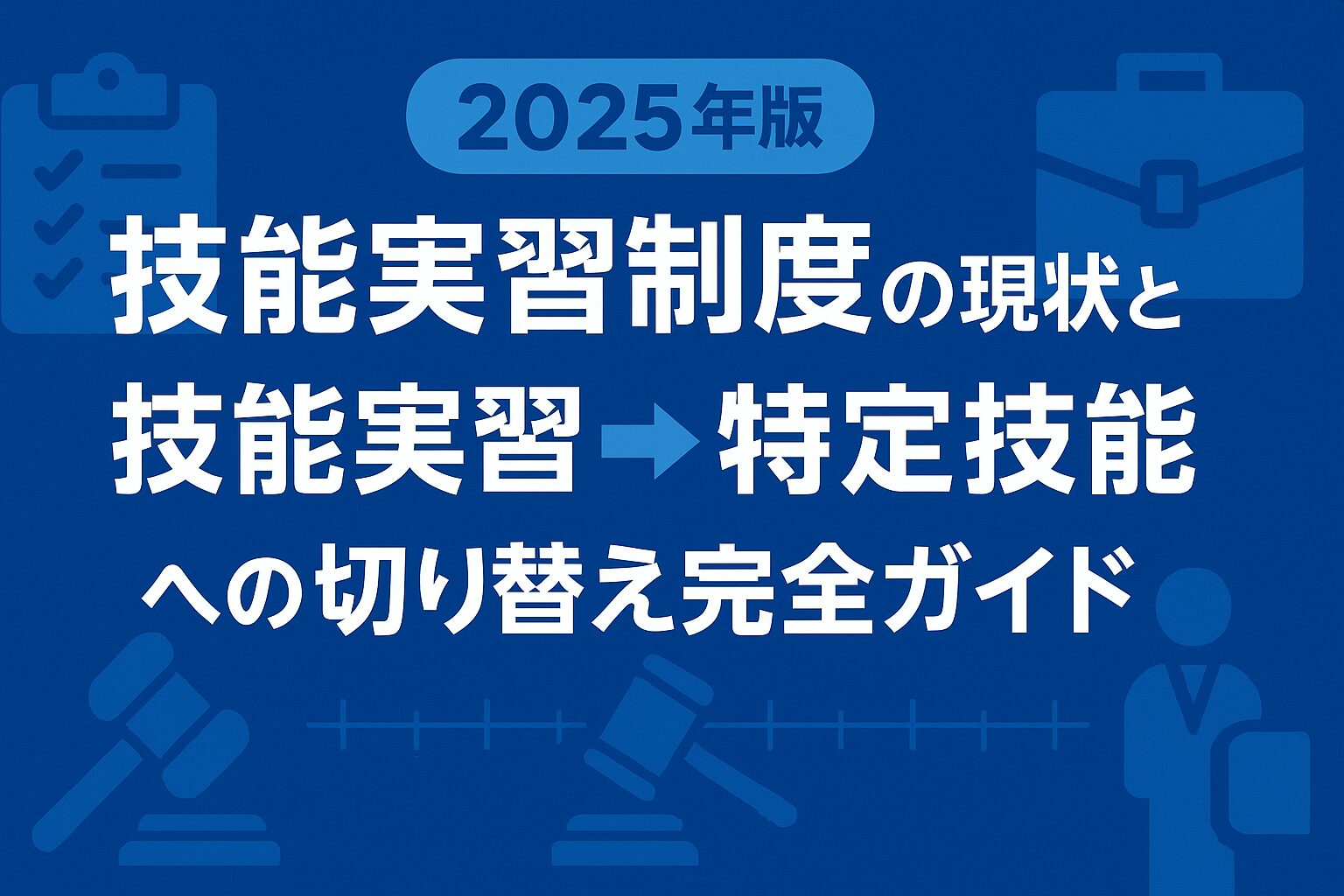
日本の外国人受け入れは、技能実習制度の発展的解消 → 新制度「育成就労」へと大きく転換が進んでいます。並行して、現場の人手不足を直接補う在留資格「特定技能」は運用改善と2号区分の拡大が続き、長期就労・家族帯同まで見据えた活用が可能になりつつあります。本記事では、2025年時点の最新動向を踏まえ、実務視点で「現状」と「切り替え手順」をまとめます。(2024年に関連法が成立。新制度の本格施行は2027年目安)
目次
1. まず押さえる全体図(2025年の整理)
- 技能実習制度:「国際貢献」から始まった制度は、育成就労制度の創設により発展的に解消へ。施行は公布後3年以内(目安:2027年4月)。移行期は数年かけて並走。
- 特定技能(1号/2号):人手不足分野での就労特化の在留資格。運用・分野は更新が続き、2025年も告示改正・要領更新・届出の見直しが実施。
- 2号の拡大:長期就労・家族帯同が可能な特定技能2号の対象分野が段階的に拡大。最新の運用は逐次確認が必要。
2. 「技能実習」→「育成就労」→「特定技能」の位置づけ比較
| 項目 | 技能実習(現行) | 育成就労(新制度) | 特定技能(1号 / 2号) |
|---|---|---|---|
| 制度目的 | 国際貢献(人づくり) | 現場での就労を通じた人材育成と確保 | 人手不足分野の即戦力確保 |
| 就労の考え方 | 実習中心 | 就労+育成(転籍の柔軟化 等) | 就労中心(分野別に職務を明確化) |
| 在留の射程 | 段階的(原則上限あり) | 詳細は告示等で順次具体化 | 1号:通算5年/2号:上限なし・家族帯同可(要件) |
※ 施行時期・運用詳細は今後の告示・要領で確定。最新の公的資料を必ず確認。
3. 企業が今すぐ理解すべき「特定技能」更新・運用の要点
- 分野・要領の更新が頻繁:分野別「運用方針・要領」や届出ルールは2025年も改定あり。採用前に最新版を確認。
- 2号の利点:長期雇用・家族帯同が可能に(対象分野・要件あり)。人材の定着・キャリア形成に直結。
- 受入れ体制:1号は支援計画・届出等の実務が必須。未経験企業は登録支援機関の活用が一般的。2号は支援義務が簡略化。
4. 「技能実習」から「特定技能」へ切り替える実務ステップ
- 対象人材の要件確認:分野の特定技能評価試験(学科・実技)合格、または実習修了要件などの経路を整理(日本語要件を含む)。
- 職務・シフトの整合:求人票・雇用契約・職務記述書(JD)を分野要領に合わせて作成。付随業務の範囲・割合も明示。
- 処遇の明確化:基本給・各手当・控除・寮費・想定手取り、所定/変形労働時間、割増率、休日運用を本文または別紙で明文化。
- 支援体制の準備(1号):生活ガイダンス、住居確保、相談体制、日本語学習等。未経験企業は登録支援機関と役割分担。
- 在留手続:在留資格変更(or 更新)申請。必要書類・届出は最新の省令・告示に準拠。
5. 現役の実習生・受入企業向け Q&A(要点だけ)
Q1. 実習から特定技能へ移る最短ルートは?
A. 分野の評価試験(+日本語)に合格し、就労要件に合う職務で雇用契約を締結。申請書類の整合(JD・契約・支援計画 等)が通過のカギ。
Q2. 2号へ上げるメリットは?
A. 在留上限なし・家族帯同可(要件)。「監督・指導」等の上位職務を想定。分野の拡大が進むため、キャリア設計がしやすい。
Q3. 制度移行(育成就労)に向けて今やることは?
A. 直近の採用は特定技能の最新運用に合わせるのが実務的。並行して、育成就労の二次情報(告示・要領)を追い、契約書式・社内規程をアップデート準備。
6. つまずきを防ぐチェックリスト(コピペOK)
- □ 分野の最新要領・告示を入管庁サイトで確認した(求人前/申請前)。
- □ JD・契約・支援計画の職務整合(付随業務の割合・シフト含む)を文書化した。
- □ 賃金内訳・控除・寮費、想定手取り、所定/変形時間、割増率を明示した。
- □ 1号の支援体制(社内or登録支援機関)を確保した。
- □ 2号活用のキャリアパス(評価試験・役割要件・賃金テーブル)を作成した。
7. 最新情報の確認先
- 出入国在留管理庁|特定技能制度:分野別要領・告示・運用改善・届出。
- 厚生労働省|外国人技能実習・見直し関連:見直し情報・関連リンク。
- JITCO|育成就労制度:制度概要・移行スケジュールの目安。
まとめ
いま採用・運用で主役となるのは「特定技能」。一方で、技能実習は育成就労制度へと舵切りが進んでおり、2027年施行を見据えた社内規程・契約フォーマットの刷新が必須です。直近の採用案件は特定技能の最新運用で安定させつつ、数年先を見据えた制度移行に備えましょう。制度は更新が続くため、申請前に公的サイトで最新情報の再確認を忘れずに。
※本記事は2025年9月時点の公開情報に基づく一般的解説です。個別案件の要件は分野・地域・時期で異なります。最新の告示・運用要領を必ず確認し、専門家へご相談ください。
株式会社オーティル


【2025年最新版】特定技能と技能実習の違い|採用前に知っておきたい6つのポイント
特定技能と技能実習の違い|企業が知っておくべき制度のポイント 日本では外国人材を受け入れる制度として「技能実習」と「特定技能」の2つがよく知られています。どちらも…
