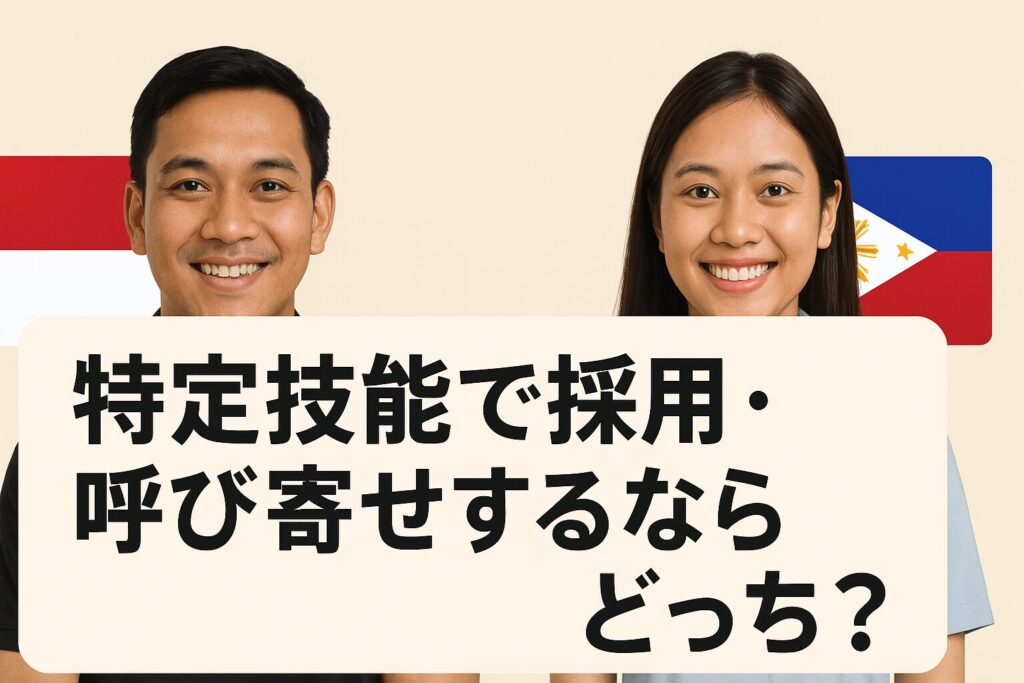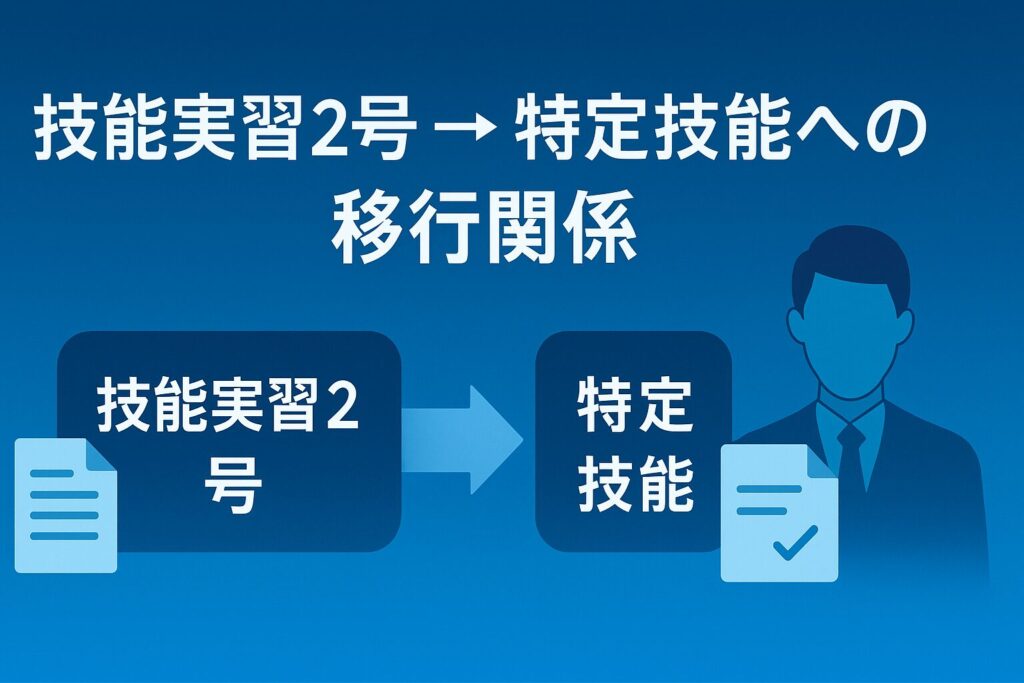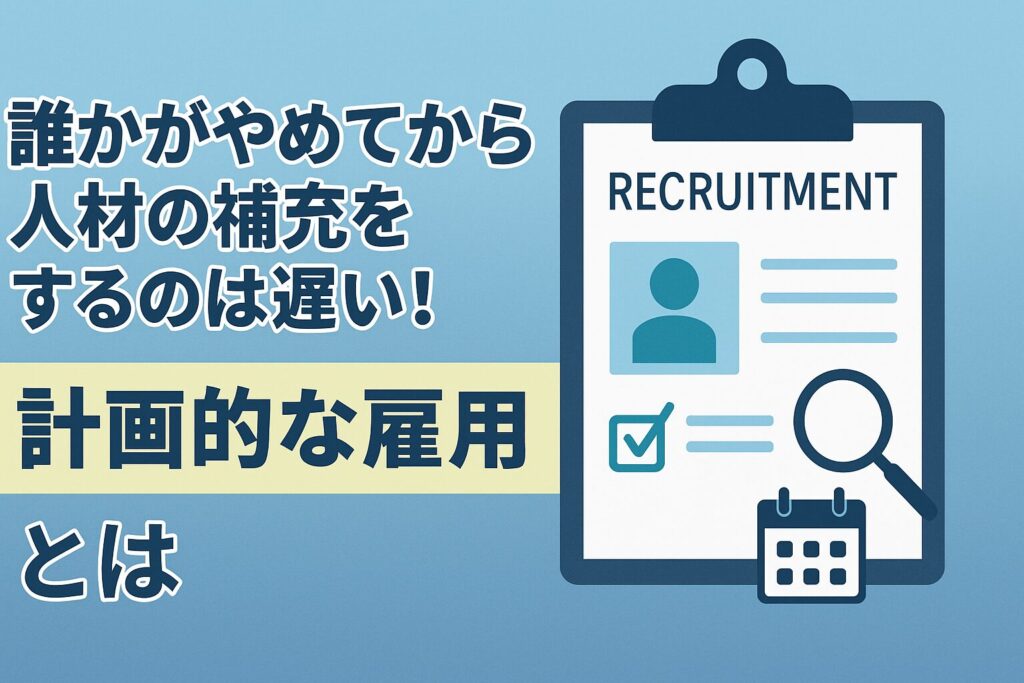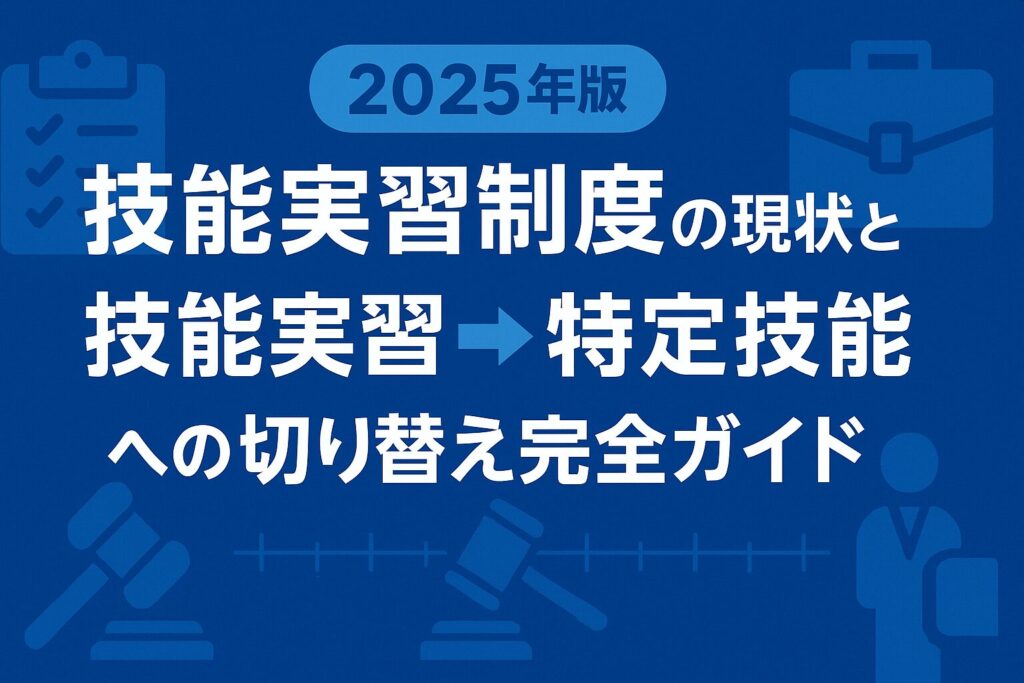外国人材の受け入れを
可能にする仕組みとは?
外国人材の受け入れを
可能にする仕組みとは?
日本で外国人材を受け入れるためには、法律に基づいた「在留資格」が必要です。中でも、深刻な人手不足が続く業種を中心に、即戦力となる外国人を受け入れるための制度として注目されているのが「特定技能制度」です。
この制度では、一定の技能水準と日本語能力を備えた外国人が、日本国内の企業と直接雇用契約を結ぶことが可能になります。従来の研修型制度とは異なり、実際の業務を担う労働者としての受け入れを前提とした仕組みです。
企業は、外国人労働者を日本人と同等以上の待遇で雇用する必要があり、単なる労働力としてではなく、共に育ち、共に働く“仲間”として迎える姿勢が求められます。
このように、「特定技能制度」は、日本社会の課題である人手不足の解消と、多様な人材との共生を同時に実現するための新たな仕組みとして、重要な役割を果たしています。


日本で外国人材を受け入れるためには、法律に基づいた「在留資格」が必要です。中でも、深刻な人手不足が続く業種を中心に、即戦力となる外国人を受け入れるための制度として注目されているのが「特定技能制度」です。
この制度では、一定の技能水準と日本語能力を備えた外国人が、日本国内の企業と直接雇用契約を結ぶことが可能になります。従来の研修型制度とは異なり、実際の業務を担う労働者としての受け入れを前提とした仕組みです。
企業は、外国人労働者を日本人と同等以上の待遇で雇用する必要があり、単なる労働力としてではなく、共に育ち、共に働く“仲間”として迎える姿勢が求められます。
このように、「特定技能制度」は、日本社会の課題である人手不足の解消と、多様な人材との共生を同時に実現するための新たな仕組みとして、重要な役割を果たしています。
制度の運用主体と構造
制度の運用主体と構造

特定技能制度は、出入国在留管理庁(法務省)が制度全体を所管し、企業・登録支援機関・地方出入国在留管理局と連携して運用されています。外国人が安心して働き、暮らすための支援体制の整備が義務づけられているのが特徴です。
- 制度創設・管理:出入国在留管理庁(法務省)
- 在留資格の種類:特定技能1号・2号
- 対象分野:14の特定産業分野(介護、外食、建設など)
- 雇用形態:企業による直接雇用(派遣不可)
- 支援義務:企業が「支援計画」を策定(登録支援機関に委託可)
- 支援機関:登録支援機関(国の基準を満たした法人や団体)
特定技能外国人を受け入れる企業は、以下の内容を含む「支援計画」を策定・実施する義務があります。
- 入国時の空港出迎え
- 行政手続きへの同行(住民登録・保険など)
- 住居の確保と生活オリエンテーションの実施
- 日本語学習の支援
- 労働・生活・健康に関する相談窓口の設置
- 月1回以上の定期面談と記録報告
※多くの企業では、これらの業務を「登録支援機関」に委託しています。


特定技能外国人を受け入れる企業は、以下の内容を含む「支援計画」を策定・実施する義務があります。
- 入国時の空港出迎え
- 行政手続きへの同行(住民登録・保険など)
- 住居の確保と生活オリエンテーションの実施
- 日本語学習の支援
- 労働・生活・健康に関する相談窓口の設置
- 月1回以上の定期面談と記録報告
※多くの企業では、これらの業務を「登録支援機関」に委託しています。
対象となる外国人と
受け入れ可能な国
対象となる外国人と
受け入れ可能な国
対象となる外国人
対象となる外国人
特定技能制度で働くことができるのは、以下のいずれかに該当する外国人です。
- 技能評価試験および日本語試験に合格した者
- 技能実習2号を良好に修了した者(一部業種で試験免除)
この制度は「未経験者の大量受け入れ」を目的としたものではなく、一定の知識と技能を持つ即戦力人材を受け入れるための選抜制度です。
受け入れ可能な国
受け入れ可能な国
現在、特定技能の二国間協定に基づいて受け入れ可能な国は以下の14か国です。
フィリピン・ベトナム・インドネシア・ミャンマー・カンボジア・ネパール・スリランカ・バングラデシュ・モンゴル・パキスタン・ウズベキスタン・タイ・ラオス・インド
これらの国々から来日する人材は、現地政府が認可した送り出し機関(Sending Organization)を通じて手続きを行います。
送り出し機関は、事前の教育・書類審査・企業マッチングを担い、適切な人材の供給と制度の健全性を支えています。
対象となる14の
特定産業分野
対象となる14の
特定産業分野

外食業
飲食店での調理補助、接客、配膳など

建設業
型枠施工、鉄筋施工、塗装など(分野別に細分化)

宿泊業
ホテルでの接客、清掃、フロント業務など

介護
介護施設での身体介助・生活支援など

漁業
養殖業、漁労作業、水産加工など

農業
耕種農業・畜産農業(収穫、飼育管理など)

飲食料品製造業
食品加工、包装、品質検査など

自動車整備業
自動車の点検・修理・整備作業

航空業
空港グランドハンドリング、機体整備補助など

造船・船用工業
溶接、仕上げ、塗装、機械加工など

ビルクリーニング
商業施設やビルの清掃作業

素形材産業
金属プレス加工、鋳造、溶接など

産業機械製造業
機械組立、仕上げ、検査など

電気・電子
情報関連産業
電子機器の製造、組立、検査など
特定技能制度の主な特徴
特定技能制度の
主な特徴
| 目的 | 人手不足の深刻な分野において、即戦力の外国人労働者を受け入れる制度 |
| 雇用形態 | 企業による直接雇用のみ(派遣不可) |
| 在留期間 | 特定技能1号:最大5年 特定技能2号:更新可能・実質的に無期限 |
| 家族帯同 | 1号:不可/2号:可能(配偶者・子) |
| 支援義務 | 受け入れ企業は「支援計画」の策定と実施が必須(外部委託可) |
| 対象者 | 試験合格者または技能実習2号修了者 |
| 企業の姿勢 | 単なる労働力ではなく、日本人と同じように“育て・支える”視点が求められる |
| 目的 | 人手不足の深刻な分野において、即戦力の外国人労働者を受け入れる制度 |
| 雇用形態 | 企業による直接雇用のみ(派遣不可) |
| 在留期間 | 特定技能1号:最大5年 特定技能2号:更新可能・実質的に無期限 |
| 家族帯同 | 1号:不可/2号:可能(配偶者・子) |
| 支援義務 | 受け入れ企業は「支援計画」の策定と実施が必須(外部委託可) |
| 対象者 | 試験合格者または技能実習2号修了者 |
| 企業の姿勢 | 単なる労働力ではなく、日本人と同じように“育て・支える”視点が求められる |
特定技能1号と2号の違い(簡易比較)
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 在留期間 | 最長5年 | 更新可・無期限 |
| 家族帯同 | 不可 | 可能(配偶者・子) |
| 技能水準 | 基本的な知識・技能 | 熟練レベル |
| 対象分野 | 14分野 | 現在は建設・造船分野のみ(今後拡大予定) |
この制度の概要を理解することで、自社に合った人材活用の選択肢として
特定技能を導入するべきかどうか、また導入後に必要な準備が何かを把握できます。
特定技能1号と2号の違い(簡易比較)
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 在留期間 | 最長5年 | 更新可・無期限 |
| 家族帯同 | 不可 | 可能(配偶者・子) |
| 技能水準 | 基本的な知識・技能 | 熟練レベル |
| 対象分野 | 14分野 | 現在は建設・造船分野のみ(今後拡大予定) |
この制度の概要を理解することで、自社に合った人材活用の選択肢として
特定技能を導入するべきかどうか、また導入後に必要な準備が何かを把握できます。
無料相談・資料請求
「まずは話を聞いてみたい」「サービス内容を詳しく知りたい」という方に向けて、
30分の無料相談(Zoom)とPDF資料の無料ダウンロード をご用意しています。
また、ご希望であれば直接お伺いしてご説明いたします。お気軽にお申し付けください。
無料相談・資料請求
「まずは話を聞いてみたい」「サービス内容を詳しく知りたい」という方に向けて、30分の無料相談(Zoom)とPDF資料の無料ダウンロード をご用意しています。
また、ご希望であれば直接お伺いしてご説明いたします。お気軽にお申し付けください。
特定技能の資格取得要件
特定技能の
資格取得要件
外国人が特定技能の資格を取得するには、次のいずれかのルートを満たす必要があります。
外国人が特定技能の資格を取得するには、次のいずれかのルートを満たす必要があります。
❶ 技能評価試験+日本語試験に合格
❶ 技能評価試験+日本語試験
に合格
技能評価試験:
各分野(介護・外食・建設など)ごとに設定された試験。必要な知識や作業手順を確認する実務テストです。
日本語試験:
原則として、以下いずれかの試験に合格が必要です。
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
❷ 技能実習2号を良好に修了
❷ 技能実習2号を良好に修了
- 同一業種で技能実習2号を終えた人材は、特定技能1号に試験免除で移行できるケースがあります。
- 多くの実習修了者がこのルートで特定技能へ移行しています。
対象年齢・学歴・経歴について
特定技能制度では、年齢・学歴の制限はありません。
ただし、一部の国では現地の送り出し機関が独自条件(年齢上限など)を設けているため注意が必要です。
試験の実施方法と場所
- 技能試験・日本語試験は、日本国内および海外の主要都市で随時実施。
- 試験内容は基本的に日本語で行われますが、一部国では補助的に母国語資料を併用するケースもあります。
- 試験情報(会場・日程など)は、各分野の主管官庁または試験実施機関のHPで確認可能です。
企業側が知っておくべきポイント
特定技能は“誰でも簡単に働ける制度”ではありません。
一定の技能・語学力を備えた外国人材を対象としており、企業側にも受け入れ体制や要件への理解が求められます。
特定技能と技能実習の違い
特定技能と
技能実習の違い
外国人材を受け入れる制度として「技能実習」と「特定技能」はよく比較されますが、
その目的や仕組み、雇用関係には大きな違いがあります。
外国人材を受け入れる制度として「技能実習」と「特定技能」はよく比較されますが、
その目的や仕組み、雇用関係には大きな違いがあります。
| 特定技能 | 技能実習 | |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 日本国内の人手不足を補うための労働力確保 | 技能移転を通じた開発途上国への国際貢献 |
| 在留資格の種類 | 特定技能1号/2号 | 技能実習1号~3号 |
| 在留期間 | 1号:最大5年 2号:更新制(期間の上限なし) | 最長5年(段階を経て延長) |
| 家族の帯同 | 1号:不可 2号:可能(配偶者・子供) | 原則不可 |
| 対象職種 | 14分野(介護・外食・建設など) | 87職種156作業(製造業・農業など) |
| 雇用形態 | フルタイムの労働者(即戦力) | 技能習得のための訓練的就労 |
| 待遇 | 日本人と同等以上の待遇義務あり | 実習生としての基準(最低賃金以上) |
| 試験の有無 | 技能評価試験+日本語試験(N4相当)必須(※移行除く) | 原則不要(送り出し国による) |
| 転職の可否 | 一定条件下で可能(分野内・同一職種) | 原則不可(所属機関変更は制限あり) |
| 受け入れ企業の義務 | 支援計画の実施(生活・労働支援10項目) | 実習計画の作成と遵守義務 |
| 制度の評価 | 労働者としての制度/実態に合っている | 実習生の権利侵害や逃亡など問題も多い |
| 今後の方向性 | 増加傾向・2号への移行も進む見込み | 改廃予定(2027年頃に廃止・一本化の可能性あり) |
技能実習を修了した外国人は、同一業種であれば試験免除で特定技能1号へ移行可能です。
特定技能1号で一定の条件を満たせば、2号へ移行して長期在留や家族帯同も可能になります。
- 技能実習:国際協力的な側面を重視し、教育・訓練の位置づけで導入したい企業向け。
- 特定技能:即戦力人材を雇用し、長期的に職場に定着してほしい企業向け。
それぞれの制度にはメリットと制限があるため、受け入れ目的や職場環境に応じた制度の選択が重要です。
| 特定技能 | 技能実習 | |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 日本国内の人手不足を補うための労働力確保 | 技能移転を通じた開発途上国への国際貢献 |
| 在留資格の種類 | 特定技能1号/2号 | 技能実習1号~3号 |
| 在留期間 | 1号:最大5年 2号:更新制(期間の上限なし) | 最長5年(段階を経て延長) |
| 家族の帯同 | 1号:不可 2号:可能(配偶者・子供) | 原則不可 |
| 対象職種 | 14分野(介護・外食・建設など) | 87職種156作業(製造業・農業など) |
| 雇用形態 | フルタイムの労働者(即戦力) | 技能習得のための訓練的就労 |
| 待遇 | 日本人と同等以上の待遇義務あり | 実習生としての基準(最低賃金以上) |
| 試験の有無 | 技能評価試験+日本語試験(N4相当)必須(※移行除く) | 原則不要(送り出し国による) |
| 転職の可否 | 一定条件下で可能(分野内・同一職種) | 原則不可(所属機関変更は制限あり) |
| 受け入れ企業の義務 | 支援計画の実施(生活・労働支援10項目) | 実習計画の作成と遵守義務 |
| 制度の評価 | 労働者としての制度/実態に合っている | 実習生の権利侵害や逃亡など問題も多い |
| 今後の方向性 | 増加傾向・2号への移行も進む見込み | 改廃予定(2027年頃に廃止・一本化の可能性あり) |
技能実習を修了した外国人は、同一業種であれば試験免除で特定技能1号へ移行可能です。特定技能1号で一定の条件を満たせば、2号へ移行して長期在留や家族帯同も可能になります。
- 技能実習:国際協力的な側面を重視し、教育・訓練の位置づけで導入したい企業向け。
- 特定技能:即戦力人材を雇用し、長期的に職場に定着してほしい企業向け。
それぞれの制度にはメリットと制限があるため、受け入れ目的や職場環境に応じた制度の選択が重要です。
採用までのタイムライン
(最短約2.5〜3ヶ月)
採用までのタイムライン
(最短約2.5〜3ヶ月)
0週〜1週目
打ち合わせ・契約
- 人数・職種・希望時期などのヒアリング
- 見積提示・契約締結
- 登記簿謄本や許認可証の提出・翻訳手配
1週〜3週目
求人票作成・MWO登録準備
- ジョブオーダー(求人票)作成・翻訳
- フィリピン現地エージェンシーとの契約
- 公証人役場での契約書承認
- MWO(フィリピン労働雇用省)登録用書類の提出
※書類不備や再提出がある場合は更に1〜2週間追加
4週〜6週目
現地募集・面談・人選
- MWO承認後、正式求人スタート
- 現地日本語学校・送り出し機関による候補者募集
- 候補者プロフィール提出、ZOOM面談(通訳付き)
- 採用者決定・契約書締結
7週〜8週目
在留資格(特定技能)申請
- 日本側で必要書類の整備(勤務カレンダー、保険・納税証明等)
- 入管(出入国在留管理庁)への申請
※審査期間:約10日〜2週間
9週〜11週目
OEC・ビザ発給・渡航準備
- フィリピン政府よりOEC(海外雇用許可証)取得(約2週間)
- 日本大使館にてビザ発給(約1週間)
- 渡航日程確定・航空券手配・初回オリエンテーション準備
12週目〜
来日・就労開始
- 日本到着・住居入居・生活立ち上げ支援
- 初回出勤(※任意で同行型オリエンテーション対応可)
想定所要期間:最短 約2.5〜3ヶ月
※必要書類の収集状況や面談調整、入管処理速度により前後します
※複数名同時進行も対応可能です
0週〜1週目
打ち合わせ・契約
- 人数・職種・希望時期などのヒアリング
- 見積提示・契約締結
- 登記簿謄本や許認可証の提出・翻訳手配
1週〜3週目
求人票作成・MWO登録準備
- ジョブオーダー(求人票)作成・翻訳
- フィリピン現地エージェンシーとの契約
- 公証人役場での契約書承認
- MWO(フィリピン労働雇用省)登録用書類の提出
※書類不備や再提出がある場合は更に1〜2週間追加
4週〜6週目
現地募集・面談・人選
- MWO承認後、正式求人スタート
- 現地日本語学校・送り出し機関による候補者募集
- 候補者プロフィール提出、ZOOM面談(通訳付き)
- 採用者決定・契約書締結
7週〜8週目
在留資格(特定技能)申請
- 日本側で必要書類の整備(勤務カレンダー、保険・納税証明等)
- 入管(出入国在留管理庁)への申請
※審査期間:約10日〜2週間
9週〜11週目
OEC・ビザ発給・渡航準備
- フィリピン政府よりOEC(海外雇用許可証)取得(約2週間)
- 日本大使館にてビザ発給(約1週間)
- 渡航日程確定・航空券手配・初回オリエンテーション準備
12週目〜
来日・就労開始
- 日本到着・住居入居・生活立ち上げ支援
- 初回出勤(※任意で同行型オリエンテーション対応可)
想定所要期間:最短 約2.5〜3ヶ月
※必要書類の収集状況や面談調整、入管処理速度により前後します
※複数名同時進行も対応可能です
無料相談・資料請求
「まずは話を聞いてみたい」「サービス内容を詳しく知りたい」という方に向けて、
30分の無料相談(Zoom)とPDF資料の無料ダウンロード をご用意しています。
また、ご希望であれば直接お伺いしてご説明いたします。お気軽にお申し付けください。
無料相談・資料請求
「まずは話を聞いてみたい」「サービス内容を詳しく知りたい」という方に向けて、30分の無料相談(Zoom)とPDF資料の無料ダウンロード をご用意しています。
また、ご希望であれば直接お伺いしてご説明いたします。お気軽にお申し付けください。
コスト概要
コスト概要
初期導入費用
採用計画の設計、求人票作成、MWO登録、公証手続き、日本語翻訳対応、OEC・ビザ取得支援などを含む一括対応。
目安:1人あたり 250,000〜300,000円
初回オリエンテーション費用(任意)
初出勤時にタガログ語対応スタッフが同行し、業務説明や職場サポートを実施。
・半日(約3時間):50,000円
・1日(約6時間):100,000円
月額支援費用(登録支援機関業務)
生活相談、行政手続きサポート、3ヶ月ごとの面談、定着支援、入管報告などの継続支援。
目安:1人あたり 月額20,000〜30,000円
航空券・ビザ関連費用(実費)
フィリピンからの渡航に必要な航空券代、ビザ発行費用などは実費で別途発生します。
その他、初期費用に含まれているもの
・健康診断費用(フィリピン国内)
・出国前オリエンテーション費用(現地で実施)
特定技能でよくある質問
特定技能で
よくある質問
Q1. 特定技能と技能実習の違いは何ですか?
A. 技能実習は「母国への技能移転」が目的ですが、特定技能は日本の人手不足を補うための“労働目的”の制度です。特定技能では外国人を即戦力として直接雇用でき、待遇も日本人と同等以上が求められます。
Q2. 特定技能の外国人は何年まで働けますか?
A. 特定技能1号は最長5年まで在留可能です。さらに高度なスキルを持つ場合は、特定技能2号に移行することで在留期間に上限がなくなり、家族の帯同も可能になります。
Q3. どのような業種で特定技能の外国人を雇用できますか?
A. 現在、14の特定産業分野(介護、外食、農業、建設、製造など)での受け入れが可能です。各分野ごとに、技能試験や日本語試験に合格する必要があります。
Q4. 登録支援機関とは何ですか?
A. 登録支援機関とは、企業の代わりに特定技能外国人への生活支援や相談対応、行政手続きのサポートなどを行う法務省に登録された支援事業者です。支援業務は企業に義務付けられているため、多くの企業が登録支援機関に委託しています。
Q5. 特定技能外国人は転職できますか?
A. はい、特定技能外国人は条件を満たせば転職が可能です。
同じ業種内であれば、転職しても在留資格は継続可能です。転職後は14日以内に入管への届出が必要です。
異なる業種への転職は、改めてその分野の技能試験・日本語試験に合格する必要があります。
ただし、雇用条件の整備や支援計画の引き継ぎなどもあるため、転職を希望する場合は、事前に登録支援機関や専門家に相談することをおすすめします。
無料相談・資料請求
「まずは話を聞いてみたい」「サービス内容を詳しく知りたい」という方に向けて、
30分の無料相談(Zoom)とPDF資料の無料ダウンロード をご用意しています。
また、ご希望であれば直接お伺いしてご説明いたします。お気軽にお申し付けください。
無料相談・資料請求
「まずは話を聞いてみたい」「サービス内容を詳しく知りたい」という方に向けて、30分の無料相談(Zoom)とPDF資料の無料ダウンロード をご用意しています。
また、ご希望であれば直接お伺いしてご説明いたします。お気軽にお申し付けください。