【保存版】特定技能制度とは?仕組み・対象業種・採用方法まで全網羅(2025年最新版)
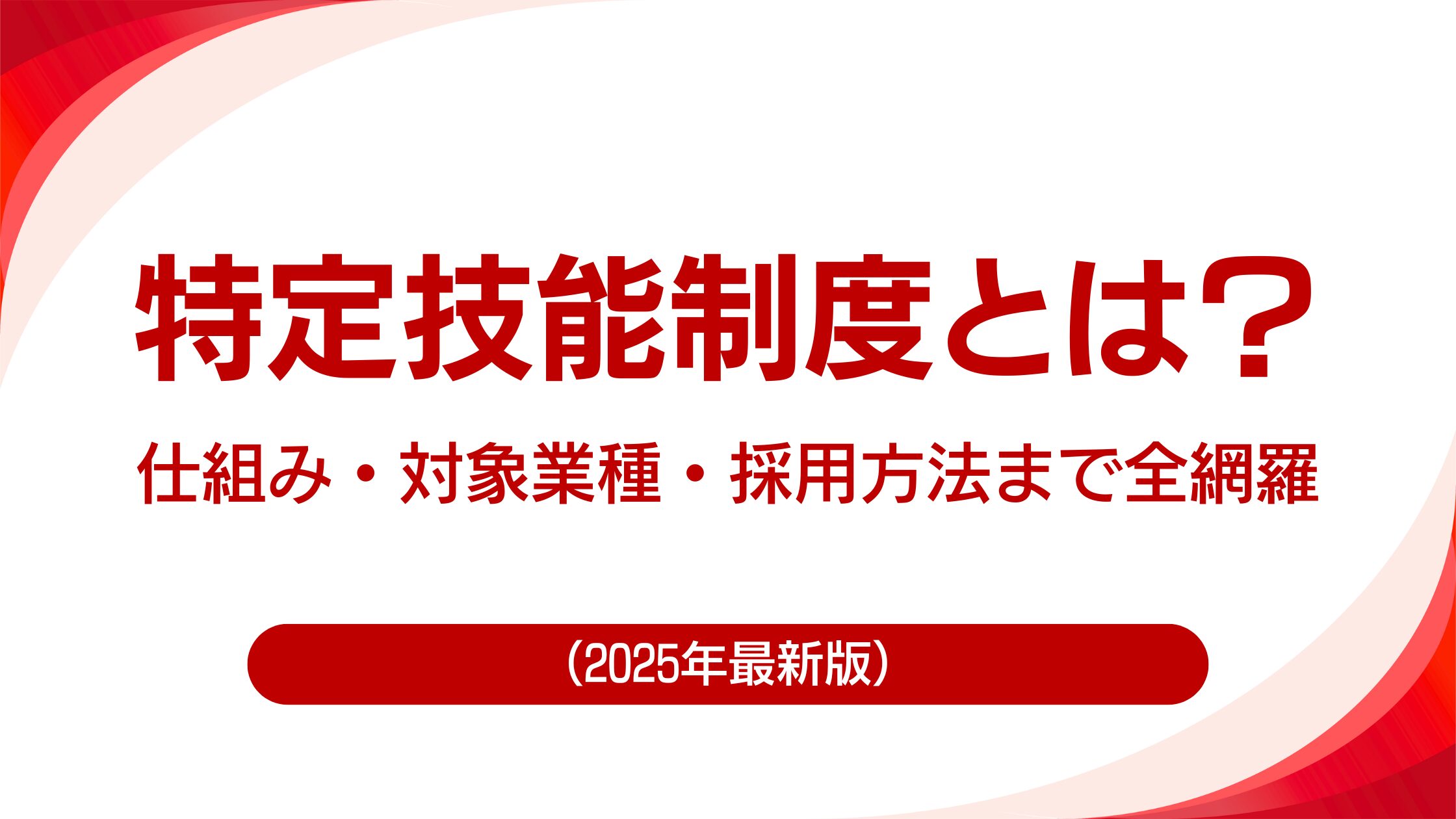
著者:株式会社オーティル
人手不足に悩む業界で注目されている「特定技能制度」。
しかし、制度の仕組みや対象業種、採用の流れなどが複雑で「正しく理解できていない」「活用できていない」と感じる企業担当者も少なくありません。
本記事では、制度の全体像から具体的な採用方法、制度活用のメリット・注意点まで、企業目線でわかりやすくまとめました。2025年最新情報にも対応した保存版の解説です。これから外国人採用を検討する企業の方は、ぜひ最後までご覧ください。
特定技能制度とは?基本の仕組みをわかりやすく解説
特定技能制度は、国内の深刻な人手不足に対応するため、専門的な技能を持つ外国人材を即戦力として受け入れることを目的とした在留資格です。まずは、制度の基本的な仕組みを理解しましょう。
制度の目的と背景
特定技能制度は、生産性向上や国内での人材確保の取り組みを行ってもなお、人材の確保が困難な状況にある特定の産業分野において、外国人材の受け入れを目的として2019年4月に創設されました。
少子高齢化による労働人口の減少という社会構造的な課題を背景に、特に人手不足が深刻な分野で、企業の事業継続と経済の発展を支える重要な役割を担っています。
対象となる在留資格「特定技能1号・2号」
特定技能には「1号」と「2号」の2種類の在留資格があり、技能水準や在留期間、家族の帯同可否などが異なります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 特定の産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能 | 特定の産業分野において、熟練した技能 |
| 在留期間 | 通算で上限5年(1年、6ヶ月または4ヶ月ごとに更新) | 上限なし(3年、1年または6ヶ月ごとに更新) |
| 家族の帯同 | 原則として認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
| 対象分野 | 12分野 | 1号の対象分野のうち、「介護」を除く11分野 |
2023年の制度改正により、特定技能2号の対象分野が大幅に拡大され、より長期的な就労と定着が可能になりました。これにより、企業は腰を据えた人材育成と安定した雇用を実現しやすくなっています。
技能実習との違い
特定技能とよく比較される制度に「技能実習」がありますが、両者は目的が根本的に異なります。
- 技能実習制度 : 日本で培った技能や知識を母国に持ち帰り、経済発展に貢献してもらう「国際貢献」が目的です。原則として転職は認められません。
- 特定技能制度 : 日本国内の「人手不足の解消」を目的とした労働力の確保です。同一分野内での転職が可能です。
つまり、技能実習が「研修生」としての側面が強いのに対し、特定技能は「労働者」として即戦力での活躍が期待される制度です。
特定技能の対象分野と求められる条件
特定技能人材を受け入れられる産業分野は、人手不足が特に深刻な分野に限定されています。
対象となる12分野の一覧
2025年現在、特定技能の対象は以下の12分野です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
※2024年に大きな見直しがあり、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野が追加され、既存の3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)が統合されました。この変更により、より多くの業種で特定技能人材の活躍が可能になっています。
業種ごとの必要スキル・試験内容
特定技能人材として認められるには、各分野で定められた「技能測定試験」に合格し、専門知識・スキルがあることを証明する必要があります。
(例)
介護分野 : 「介護技能評価試験」
外食業分野 : 「外食業技能測定試験」
建設分野 : 「建設分野特定技能1号評価試験」
これらの試験に合格することで、即戦力として業務に従事できる能力があることを客観的に示します。
日本語能力や実務経験の要件
技能面に加え、業務や日常生活に必要な日本語能力も求められます。
日本語能力試験 :
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
- 日本語能力試験(JLPT)のN4以上
試験の免除 :
「技能実習2号」を良好に修了した外国人は、上記の技能試験と日本語試験が免除されます。そのため、技能実習からの移行組は、企業にとって非常にスムーズに採用できる人材と言えます。
企業が特定技能人材を受け入れるメリットと課題
制度活用を成功させるためには、メリットと注意点の両方を理解しておくことが不可欠です。
人手不足の解消
最大のメリットは、何と言っても即戦力となる人材を直接雇用できる点です。技能試験と日本語試験に合格した人材であるため、基本的な業務スキルとコミュニケーション能力が担保されており、採用後の育成コストを抑えながら、迅速に人手不足を解消できます。
コスト面の特徴
採用にかかるコストは、国内在住者か海外在住者かで変動します。
- 主なコスト : 人材紹介手数料、在留資格申請費用、海外からの場合は渡航費など。
- 給与水準 : 特定技能外国人の報酬は、「日本人従業員と同等額以上」と法律で定められており、不当に安く雇用することはできません。
- 支援委託費 : 後述する「登録支援機関」に支援を委託する場合、月々の支援費用が発生します。
文化・言語面での注意点
異なる文化背景を持つ人材を受け入れる際には、コミュニケーションや生活習慣の違いへの配慮が不可欠です。
- 円滑なコミュニケーション : 専門用語や日本特有の表現を分かりやすく伝えたり、業務指示を明確にしたりする工夫が求められます。
- 生活サポート : ゴミ出しのルールや騒音問題など、日本の生活習慣に関するガイダンスも重要です。
- 社内理解の促進 : 外国人材を受け入れる目的や文化の違いについて社内で共有し、協力体制を築くことが、定着と活躍の鍵となります。
特定技能人材の採用方法と手続きの流れ
特定技能人材の採用は、大きく分けて「国内採用」と「海外採用」の2パターンがあります。
国内採用と海外採用の違い
- 国内採用 : 日本に既に在留している留学生や技能実習修了者などを採用します。
メリット: 面接がしやすく、人柄やスキルを直接確認できる。入社までの期間が短い。
デメリット: 採用競合が多く、人材の確保が難しい場合がある。 - 海外採用 : 海外にいる人材を現地で、またはオンラインで面接して採用します。
メリット: 採用対象となる母数が多く、優秀な人材を見つけやすい。
デメリット: 在留資格の取得や渡航準備に時間がかかる。渡航費などのコストが発生する。
登録支援機関の利用の有無で変わるポイント
特定技能外国人を受け入れる企業は、彼らが安定的・円滑に活動できるよう、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を行うことが義務付けられています。
- 自社で支援 : 支援責任者や担当者を選任し、法律で定められた全ての支援計画を実施します。相応の体制とノウハウが求められます。
- 登録支援機関に委託 : 支援計画の全部または一部の実施を、出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」に委託します。多くの企業はこちらを選択しています。
専門的な知識を持つ登録支援機関に委託することで、企業は採用や労務管理の負担を大幅に軽減し、本来の事業に集中できます。
申請から就労開始までの流れ
以下は、登録支援機関を利用して海外から人材を採用する場合の一般的なフローです。
<採用活動フェーズ>
- 求人依頼 : 登録支援機関に求める人材像や条件を伝え、求人を依頼します。
- 候補者の選定・面接 : 機関から紹介された候補者とオンラインなどで面接を実施します。
- 内定・雇用契約の締結 : 内定を出し、労働条件などを明記した雇用契約を締結します。
<申請・入国フェーズ>
- 支援計画の策定 : 登録支援機関が、法律に基づいた支援計画を作成します。
- 在留資格認定証明書(COE)の申請 : 地方出入国在留管理局へ必要書類を提出し、在留資格を申請します。
- COE交付・ビザ申請 : COEが交付されたら、現地の本人へ送付。本人が日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請します。
- 入国・就労開始 : ビザが発給されたら来日。空港への出迎え、住居の準備などを経て、就労開始となります。
登録支援機関の役割と選び方のポイント
制度活用の成否を左右するとも言えるのが、パートナーとなる登録支援機関選びです。
支援内容とは?
法律で定められた義務的支援には以下のようなものがあります。
- 事前ガイダンスの提供
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談の実施、行政機関への通報
これらの支援を適切に行うことが、人材の定着に直結します。
選定時に見るべき3つのポイント
数ある登録支援機関の中から、自社に合った機関を選ぶためには、以下の3点を確認しましょう。
- 支援実績と専門性 : 自社と同じ業種での支援実績が豊富か、最新の法改正に対応できる専門知識があるかを確認します。
- 支援体制の充実度 : 担当者のレスポンスは早いか、多言語対応(特に採用したい国籍の言語)が可能か、緊急時のサポート体制は整っているかなどをチェックします。
- 料金体系の明確さ : 月々の支援委託費のほか、どこまでが基本料金に含まれ、何がオプション料金になるのか、事前に詳細な見積もりを取り、比較検討することが重要です。
フィリピン人材を得意とする支援機関とは?
特にフィリピンからの採用を検討する場合、注意が必要です。フィリピンには、自国の海外労働者を保護するための独自の政府機関DMW(旧POEA)があり、雇用主や登録支援機関はこの機関への登録や手続きが必須となります。
この手続きは非常に煩雑で専門知識を要するため、フィリピン政府の要件を熟知し、DMW認定の現地送出機関と強力な連携を持つ登録支援機関を選ぶことが、スムーズな採用の絶対条件となります。
特定技能でよくある質問(FAQ)
- 在留期間はどれくらい?
-
「特定技能1号」は通算で上限5年です。1年、6ヶ月、4ヶ月ごとの更新が必要です。建設分野や造船・舶用工業分野などで「特定技能2号」に移行できれば、更新を続けることで在留期間の上限なく日本で就労できます。
- 家族の帯同は可能?
-
「特定技能1号」では、原則として家族(配偶者や子)を日本に呼び寄せることはできません。「特定技能2号」の資格を取得すれば、要件を満たすことで家族の帯同が可能になります。
- 途中で辞めたらどうなる?
-
特定技能外国人は、本人の意思で同じ業務区分の範囲内で転職することが可能です。会社都合で解雇した場合や、本人が自己都合で退職した場合は、企業はハローワークや地方出入国在留管理局への届出が必要です。また、転職先が見つかるまでの支援も登録支援機関や受入れ企業の努力義務とされています。
まとめ|特定技能制度は中長期的な人材確保の有力手段
特定技能制度は、単なる短期的な労働力の補充ではなく、適切なサポートを行うことで、企業の未来を支える貴重な人材を確保できる、中長期的な視点での有力な選択肢です。
制度を活用するために準備すべきこと
- 社内理解の醸成 : 外国人材を「仲間」として受け入れるための社内コンセンサスの形成。
- 受け入れ体制の整備 : 業務マニュアルの多言語化や、相談窓口の設置など。
- 信頼できるパートナー選び : 自社の状況に合った登録支援機関との連携。
失敗しないためのアドバイス
特定技能制度の活用で失敗しないためには、「コスト」や「手続き」といった目先の課題だけでなく、採用した人材に「長く活躍してもらう」という視点が何よりも重要です。文化や言語の壁を乗り越え、彼らが日本で安心して働き、生活できる環境を整えることが、結果的に企業の成長へと繋がります。
特定技能制度の活用、特に信頼性と実績が求められるフィリピン人材の採用をご検討中の企業様へ。
株式会社オーティルは、フィリピン政府の複雑な手続きに精通し、現地との強力なネットワークを活かした質の高い人材紹介と、手厚い支援体制に自信があります。
「何から始めればいいかわからない」
「自社に合った人材が見つかるか不安」
「手続きや支援を丸ごと任せたい」
このようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、お気軽に株式会社オーティルにご相談ください。
経験豊富な専門スタッフが、貴社の人材課題解決に向けて、貴社の状況に応じた最適なプランをご提案いたします。
人手不足の解消と企業成長の実現に向けて、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
